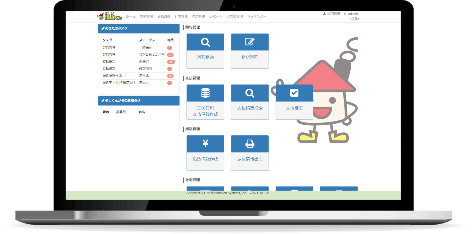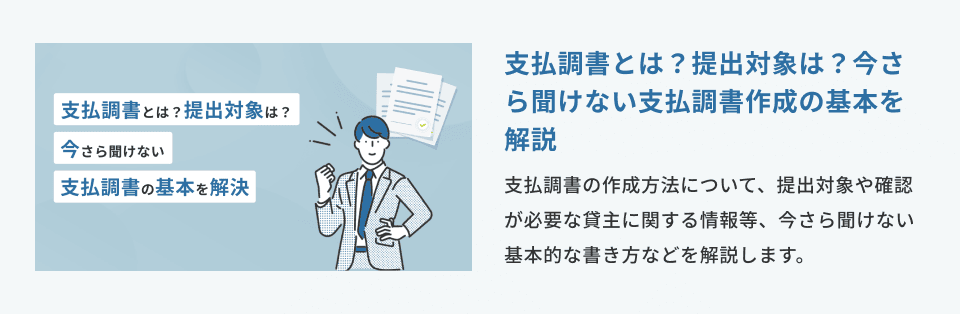社宅管理システム「借上くん」の 資料ダウンロードはこちら
コラム
社宅管理に関するお役立ち記事をまとめております。随時更新中。
教えて!借上くん‐家主からマイナンバーの提供を拒否されました!マイナンバーの必要性や対策を解説‐
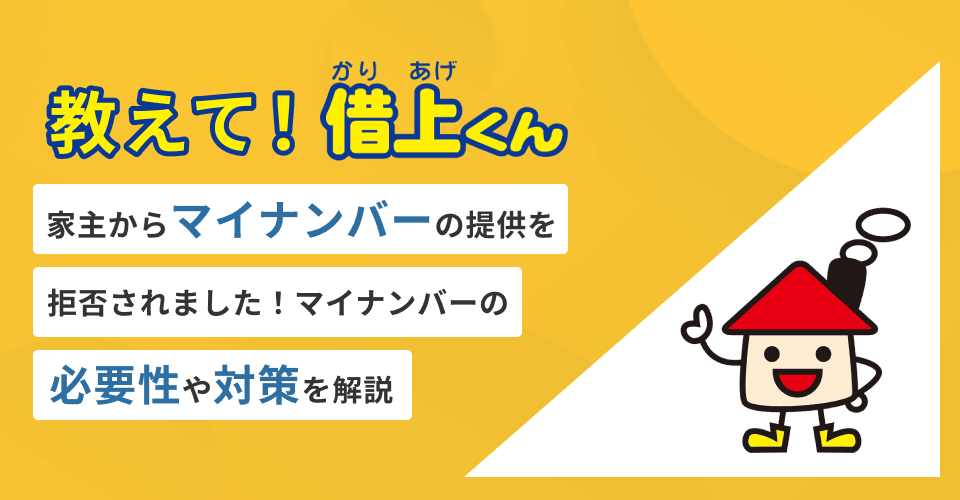
-
Q.家主(個人)からマイナンバーの提供を拒否されました。
支払調書はどのように作成すればよいのでしょうか。 -
A.
マイナンバー(個人番号)の記載は法律(国税通則法、所得税法等)で定められた義務であることを伝え、できる限り提供をお願いしましょう。
もし拒否された場合は、税務署からの問い合わせに備えて、経緯を説明できるようにしておきましょう。
■ 支払調書が必要な理由とマイナンバーの必要性
支払調書は、税務署に納税状況を申告するための書類であり、「法定調書」の一つです。同一年に支払った税金の対象や内容を報告するためのもので、提出が義務付けられています。
税務署は支払調書を通じて、事業者が納税義務を果たしているか確認します。支払調書にマイナンバーを記載することで、個人の収入の変動をより詳細に、かつタイムリーに把握でき、税金の徴収漏れを防ぐことができます。そのため、マイナンバー制度の導入目的は脱税対策とも言われており、その記載は法律(国税通則法、所得税法等)で義務付けられています。
■ マイナンバーが入手できない場合の対策は?
マイナンバーを教えてもらえない場合、マイナンバーが空欄の支払調書を提出した後、税務署からの問い合わせに対応できるように準備しておく必要があります。マイナンバー提供の依頼と、それに対する拒否についての経緯等を記録し、単なる義務違反でないことを明確にしておきます。
個人情報漏洩のリスクを理由に、マイナンバー提供を拒否された貸主に対しては、法的な規定や会社のプライバシーポリシー、実施しているセキュリティ対策を明確に伝えるなど、情報漏洩のリスクを抑える取り組みをアピールしましょう。
■ マイナンバーが記載できていない支払調書の注意点
現在はマイナンバー(家主が企業の場合は法人番号)の記載がなくても書類が受理されているケースもあるようですが、マイナンバーの記載は、法律で定められた義務です。今後の法定調書作成のために、マイナンバーの提供を拒否された方に対しても、引き続き提供依頼をしましょう。
国税庁のホームページにはリーフレットもありますので、マイナンバーの提供を依頼する時に活用するとよいでしょう。
■ マイナンバーの管理、どのようにされていますか?
マイナンバーは重要な個人情報であるため、取り扱う際には細心の注意が必要になります。
マイナンバーを適切に保護し、悪用されないようにするためにはセキュリティ対策を実施する必要がありますが、社宅業務担当者には大きな負担となります。
マイナンバー管理システムやセキュリティシステムを導入することで、マイナンバー管理業務の効率化に繋がります。
マイナンバーを安全に管理できる!
- ◆ 社宅管理業務の流れとよくある課題
- ◆ 借上くんの機能
- ◆ 導入実績など