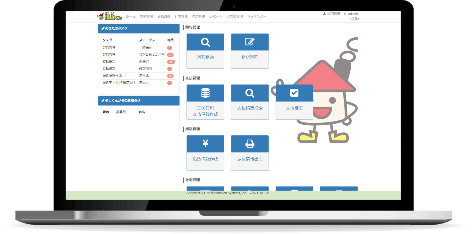社宅管理システム「借上くん」の 資料ダウンロードはこちら
コラム
社宅管理に関するお役立ち記事をまとめております。随時更新中。
福利厚生として借上げ社宅を検討しているなら知っておくべき!メリット・デメリット・導入手順
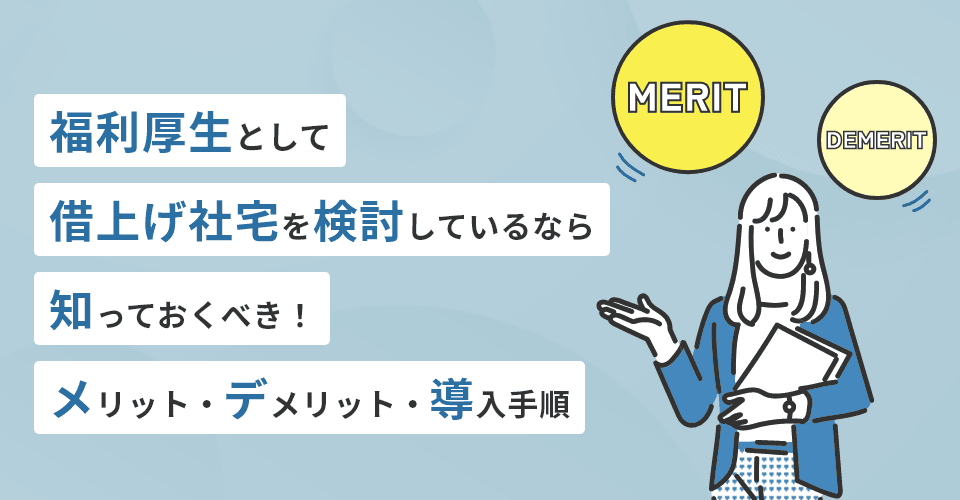
目次
1. 優秀な人材を採用するためには最強の福利厚生、借上げ社宅を導入すべき
借上げ社宅は、企業が優秀な人材を採用するために導入する最強の福利厚生の一つとなります。
複数の調査によると、企業の福利厚生の中で最も「あったら嬉しい制度」として住居サポートがあげられました。持ち家に住んでいることが多い40代以上は「住宅手当」を、一人暮らしが多い20~30代は「社宅・寮」を好むことが多いです。特に、新卒などで地方から上京した場合、初任給で家を借りるのは非常に難しく、家賃の負担もとても大きいため、借り上げ社宅は重要な選択基準になっています。
人材不足が続いている中、特に競争が激しい業界では優秀な人材を採用するために借上げ社宅制度を検討している企業が増加しています。
2. 借上げ社宅制度のメリット
借上げ社宅制度は、従業員と企業の双方にとってメリットがあります。
まず、社宅を提供することで、従業員は市場価格よりも安く住むことができます。これにより、従業員の生活費を削減し、生活水準を向上させることができます。このことは、従業員のストレスを軽減し、生産性を高めることに繋がるきっかけにもなります。
特に、工場などの深夜勤務が発生したり長距離通勤が多い場合、職場の近くに社宅を用意しておくことで従業員の通勤にかかる負担が軽減できます。転居を伴う異動が多い場合は、転居に伴う賃貸借契約を企業が代行することで従業員が通常業務に専念できます。
また、企業側にとっては、従業員が求職者の立場から自社を選ぶ際に、社宅制度があるかどうかが重要なファクターとなります。社宅制度があることで、優秀な人材の確保が期待できます。
そして、社宅制度があることで、従業員はより長期的な視点での雇用を望むようになります。このことは、企業にとって従業員の定着率向上というメリットに繋がることもあります。
他にも企業側のメリットとしては、財務上の効果も挙げられます。社宅の費用は福利厚生費となることから経費とすることができます。
3. 借上げ社宅制度のデメリット
借上げ社宅を導入する際には、従業員と企業の双方にデメリットがあることも認識する必要があります。
借上げ社宅は、企業が提供する住宅を選ぶことができますが、希望する住宅が空いていない場合や、企業が提供する住宅の中からしか選べない場合があります。また、賃貸住宅と同様に、改装やペットの飼育が制限されることもあります。
企業では、住宅に関する契約管理や賃料支払などの手続きを企業側で実施するため、担当部門の業務負荷が高くなることがあります。そのため、社宅管理において、代行サービス利用やシステム化による対策が必要となってきました。
4. 借上げ社宅を導入するために検討すべきことは?導入手順に沿って解説
借上げ社宅制度を検討して導入が決まりましたら、以下の流れに沿って様々な準備が必要です。
①導入計画を立てる
-
・予算
借上げ社宅の「会社負担額」の範囲を検討し、予算を確保します。 *既に「住宅手当」を支給している場合、現在の手当と同額を借上げ社宅の「会社負担額」とする方法もあります。 この場合、会社・従業員共に社会保険料の負担額が減額になります。
-
スケジュール
導入時期を決定します。
②社宅規程を作る
- ・対象社員(転居を伴う赴任社員など)
- ・対象ケース(赴任など)
- ・経費の負担割り(経費別の会社負担と社員負担)
- ・入居期限(最長○○年など)
- ・物件選定における注意事項(家賃の上限、不動産会社の指定、下見の経費など)
③運営方法を検討する
-
・社宅管理業務の洗い出し
契約管理・家賃支払・支払調書作成などの業務が発生します。
-
・社宅管理業務担当の決定
社内で管理するのか、社宅代行サービスを利用するのか決定します。 社内管理の場合、社宅契約管理システムを利用する場合もあります。 社宅代行サービスは、転貸(社宅管理代行会社が貸主)を利用できる場合もあります。
- ・住宅経費の会社支払いに関する経理部門との取り決め(支払いサイトなど)
- ・社員の負担額(社宅使用料)の給与控除に関する人事部門との取り決め
- ・物件斡旋依頼先(不動産会社)の選定
④従業員の同意を取り付ける
就業規則の改訂を従業員(組合)に説明し、同意を取り付けます。
⑤必要書類を準備する
社宅利用申請書、社宅物件斡旋依頼書、社宅解約申請書等の必要書類を準備します。
契約管理、支払管理、支払調書作成まで!
借上げ社宅、自社保有寮のあらゆる業務をこれ1つで
- ◆ 社宅管理業務の流れとよくある課題
- ◆ 借上くんの機能
- ◆ 導入実績など