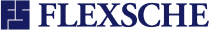コラム
生産計画の最適化ポイントを徹底解説!勘や経験に頼らない方法とは?
.png?w=950&fm=webp)
近年、グローバルサプライチェーンの推進にともない生産計画が複雑化しています。原材料の調達元や製品の販売先がグローバル化すると、計画立案で考慮すべき要素が増え、ベテラン従業員の経験のみでは対応が難しくなります。そのため「もう人の勘や経験を頼りに計画するのはムリだ」などと、課題を抱える製造関係者は多いでしょう。
そこで今回は、生産計画の役割や組み立て方、最適化ポイントを解説します。また、生産計画を効率化したいとお考えの方には、「生産スケジューラ」の導入がお勧めです。本記事では、生産スケジューラの導入効果や選定ポイントなどもご紹介します。
目次
スマートファクトリーを実現する
生産スケジューラ「FLEXSCHE」